【発達障害の中学生】具体的な困り事・親ができる7つのサポートを紹介
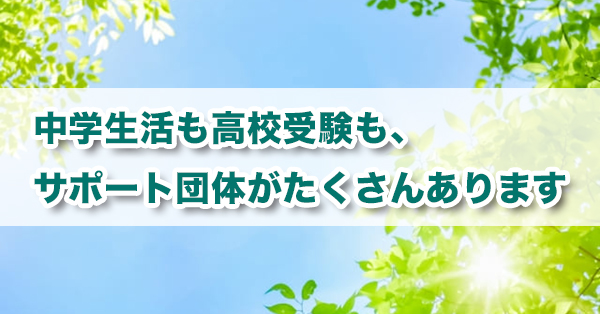
![]()
![]()
![]()
この記事では、発達障害(グレーゾーン)の中学生が抱えやすい困り事と、親御さんができる具体的なサポートをお伝えします。
一番大切なことは、お子さんのことを親御さん・ご家庭だけで対応しようとせず、学校や医療機関、サポート団体を利用して相談することです。
お子さんはもちろん、親御さんの支援を行っている人や団体はたくさんあります。
発達障害(グレーゾーン)の中学生のお子さんがいる親御さんは、ぜひ参考にしてください。
私たち、キズキは、発達障害や不登校のお子さんを、13年間で3,000名以上サポートしてまいりました。発達障害や不登校についての無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。少しでも気になるようでしたら、お気軽にご連絡ください。
目次
発達障害の中学生の困り事

発達障害とは、先天的な脳の機能の偏りによって、社会生活やコミュニケーションに困難が生じている状態のことです。(アメリカ精神医学会『DSM-V』準拠)
主な発達障害の種類
- ADHD(注意欠陥・多動性障害)
- ASD(自閉症スペクトラム障害)
- SLD(限局性学習障害)
これからお伝えする発達障害の特性の中には、程度の差はあるものの中学生なら誰にでも当てはまるものもあります。
![]()
この章では、発達障害の中学生が抱えやすい困り事を、発達障害の種類別に解説します(参考:村上由香『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に暮らすための本』)。
なお、発達障害は「病気」ではありません。
あくまでも「目立ちやすい特性がある」ということなのです。
発達障害による生活上の困り事は、専門家と相談しながら対策していくことで緩和できますので、ご安心ください。
①ADHD(注意欠陥・多動性障害)の困り事
ADHDは、正式名称を「注意欠如・多動性障害(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)」と言い、発達障害の一種です。
特性の程度や現れ方には個人差がありますが、「不注意」と「多動・衝動性」の2つの特性に伴うが困り事が多く見られます。
不注意による困り事
- 整理整頓が苦手
- 記入ミスが多い
- 忘れ物や持ち物の紛失が多い
- 確認作業がうまくいかない
多動・衝動性による困り事
- 気が散りやすく目の前のことへの集中が難しい
- 着席時も身体を動かしていないと落ちつかない
- 他人の意見を聞き終わる前に発言したり行動したりする
- 気にいらないことが起こると衝動的な行動に出ることがある
- 優先順位をつけて勉強することが苦手
- 宿題の提出締切を守ることが難しい
②ASD(自閉症スペクトラム障害)の困り事

ASD(Autism Spectrum Disorder、自閉症スペクトラム障害)とは、社会性・コミュニケーション・想像力の3つにおける特性・特徴が目立つ発達障害です。
社会性における特性・特徴
- クラスの雰囲気や人間関係にうまく気が回らない
- 先生や同級生の話を聞いていないと誤解されやすい
コミュニケーションにおける特性・特徴
- 質問の意図、身振り、比喩、冗談などを理解が苦手
- 連絡や相談がうまくできない
想像力における特性・特徴
- 決まった手順やルールに強くこだわる
- 予定が変わるとパニックになりやすい
- 暗黙のルールや明示されてない決まりに疎い
聴覚や嗅覚が過敏であることによって、大きな音(クラスメイトの声、運動会のピストルなど)や強い匂い(給食の匂いなど)などが苦手なことがあります。
ASDの中学生は、学習面では問題がなくても、コミュニケーションや人間関係などの社会性の面での困り事が多いようです。
③SLD(限局性学習障害)の困り事
SLD(限局性学習障害)とは、「読む・聞く・話す・書く・計算する・推論する」の6つの能力の1つ以上に、習得や使用の困難がある発達障害です。
ただし、文部科学省の定義では、次の条件が付きます。
視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない
つまり、「知的障害のため本を読むことが苦手」な場合は、SLDには当てはまらないのです。
SLDの中学生が抱えやすい困り事
- 授業での音読がうまくできない
- 先生が話す授業内容を聞き取って理解するのが難しい
- 板書をノートに書き写すのに苦労する
- 自分の意見をうまく話せない
- 計算問題や推論が苦手
いずれの特性にも、共通するのが「特定の情報処理が難しい」ことです。
また、「読む・聞く・話す・書く・計算する・推論する」のうち、どれに困難を覚えるのかは、一人ひとりの特性や特徴によって違ってきます。
例えば、読字障害であれば「教科書の文章をうまく読めない」、書字障害であれば「文字を書いたり覚えたりすることに苦労する」など、困難は個人によって大きく異なるのです。
![]()
発達に特性がある中学生のお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)
発達障害の中学生の勉強・受験での困り事

![]()
![]()
発達障害の中学生の勉強面での困り事
- ADHD:授業態度に問題ありと判断されて、内申点を低く付けられることがある
- ASD:クラスメイトとのコミュニケーションや協調性が求められる授業が苦手
- SLD:苦手分野によるハンデで勉強がうまく進まない
こういった状況が続くと勉強への苦手意識が強くなり、勉強をしない状態になる可能性もあります
具体的な対策としては、「学校や支援団体などに相談してサポート体制をつくること」が大切です。
特に勉強面での不安には、発達障害の中学生に指導実績のある家庭教師などを利用することがオススメです(私たちキズキもその一つです)。
そうした家庭教師では、「特性や特徴に合わせた勉強」だけでなく、内申点対策や志望校探し(お子さんに合った高校探し)、生活面などもアアドバイスをしてもらえることもあります。
発達に特性がある中学生のお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)
発達障害の中学生のために親ができる7つのサポート
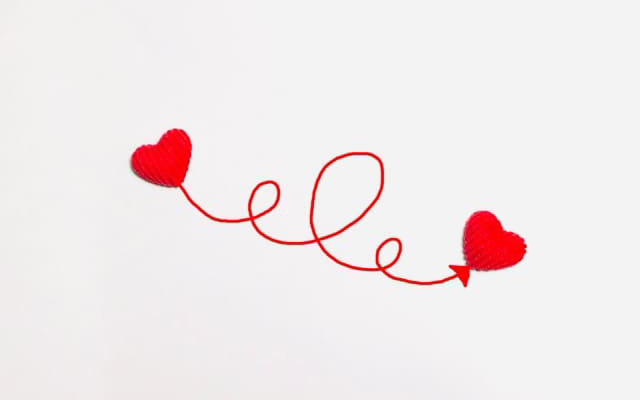
![]()
発達障害の子どもと接する際、次の2つのポイントが前提となります。
- ①親子間で「問題」を抱え込まない(学校・医療機関・サポート団体などに相談する)
- ②親御さん自身が子どもの発達障害を受け入れる
これらのことを念頭に置いた上で、お伝えするサポートを実践してみてください。
サポート①担任の先生と相談・対応を考える
![]()
中学校でのお子さんの様子に詳しい担任の先生であれば、勉強面や人間関係の悩みなど、込み入った相談ができます。
また、お子さんが通っている中学校にスクールカウンセラーが在籍していれば、そちらに相談するのもよいかもしれません。
学校でのカウンセリング機能の充実を図るために配置されている、心のケアやストレス対処の専門家。子どもだけでなく、親御さんのカウンセリングも受け付けています。
発達障害のお子さんが利用できる公的支援や、適切なサポート団体などを詳しく聞けることもあるので、まずは一度相談してみてください。
サポート②特別支援教育コーディネーターと話しあう

![]()
特別支援教育コーディネーターとは
- 通常クラスでの授業が難しい児童の支援が目的
- 学校内の関係者や福祉、医療等の関係機関との連絡・調整の役割を担っている
- 発達障害や疾患が疑われる子どもの相談に向いている
(参考:独立行政法人国立特別支援教育総合研究所※PDF「特別支援教育コーディネーターの役割・機能について」)
ただし、学校によっては設置されていない場合もあります。
まずは、特別支援教育コーディネーターが学校に在籍しているかどうか問い合わせてみてください。
サポート③サポート団体や学習塾など専門家に相談する
![]()
特に重要なのが、かかりつけの医師や臨床心理士・公認心理師などとの情報共有・協力です。
中学生になる前の幼少期から発達障害の傾向が明らかになっている場合、継続的にお子さんを診ている先生がいるでしょう。
こうした先生であれば、専門知識を有しているだけでなく、発達の経過も知っているため、お子さん個人に適したアドバイスを得られるはずです。
また、まだ医師の診断を受けていない場合は、診断を受けることを一度検討してみてください。
その他にも、発達障害の中学生を支援している公的な団体は多くあります。
発達障害の相談ができる公的団体
- 発達障害者支援センター
- 児童発達支援センター
- 精神保健福祉センター
特に、発達障害に特化した相談ができるのは、発達障害者支援センターです。
発達障害の早期発見と早期支援を目的として、本人や家族の生活をサポートする支援機関。発達障害の確定診断が下りていない場合でも、子どもに発達障害の可能性があるなら相談が可能。精神保健福祉士や社会福祉士などが在籍するところもあります。
また、発達障害の中学生の指導実績がある学習塾や家庭教師であれば、学習面だけでなく、生活面のアドバイスも得られる場合もあります(私たちキズキもその一つです)。
発達に特性がある中学生のお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)
サポート④適度に休ませる

![]()
ASDやADHDの中学生の中には、一度集中すると休み時間を取らずに、長時間の作業に取り組む「過集中」の傾向がある子どもがいます。
集中は長く続きますが、もちろん疲れは溜まっていくため、調子を崩したり倒れたりすることもあります。
お子さんが集中しすぎている様子があれば、親御さんが声を掛けて、休むように促しましょう。
参考:星野仁彦『発達障害に気づかない大人たち』
サポート⑤長所やがんばったところを褒める
![]()
中学生に限らず、発達障害の人は、特性や特徴伴う困難や失敗によって、自信を失いやすいと言われています。
しかし、お子さんが信頼する親御さんから長所やがんばったことを褒められると、自信がつき「生きやすく」なることが期待できるのです。
また、発達障害の子どものサポートを考える上では「二次障害」に配慮することも必要になります。
発達障害に関連して起こる「二次的な問題」の総称。例えば、発達障害の特性は、小学校での孤立やいじめに繋がるケースがあります。孤立・いじめ自体も二次障害ですし、孤立・いじめのストレスや不適応によるうつ病や不安障害のような病気・不登校などの「困難」も二次障害です。
こうした二次障害を防止するためにも、長所を見つけたときや、がんばって成果が出せたときなどに、積極的にお子さんを褒めてください。(参考:齊藤万比古『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』)
サポート⑥親御さん自身が発達障害の理解を深める
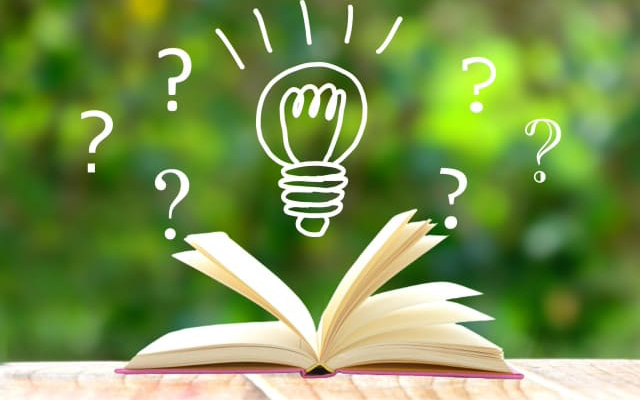
![]()
発達障害の傾向がある中学生には、一人ひとり違った特性・性格・環境などに合わせた個別の対応が必要になります。
「個別対応」の前提として、やはり「発達障害の一般知識」は身につけておいた方がよいでしょう。
発達障害の理解を深める方法としては、専門家・サポート団体への相談、関連書籍の読書などのほか、「親の会」に参加する方法もあります。
発達障害や不登校など、似た境遇にある子どもの親同士が意見交換をする場です。一般的には、地域ごとに団体や部会が分かれています。親の会に参加することで、「発達障害の子どもを持つ親と意見交換をして有益な情報を得る」「悩みを共有できて気持ちが楽になる」といったメリットが期待できます。
例えば、「JPALD(特定非営利活動法人 全国LD親の会)」では、発達障害の中でも特にSLDは、日本を6ブロックに分けて、保護者による情報交換会、勉強会、SLDの子の友達づくり、各種イベントなどを催しています。
JPALDの他にも、「発達障害 親の会」と検索すれば、多くの団体の活動を見つかりますよ。
「親の会」は、それぞれで目的や性質が異なります。そのため、一つの会が合わなくても、別の会を探してみましょう。
サポート⑦卒業後の進路や受験校について早めに調べ始める
![]()
中学卒業後の進路は高校とは限りませんが、この記事では特に高校について解説します(就職や、高校以外の学校に進学する場合も、先述のサポート団体などに相談するとアドバイスがもらえます)。
お子さんの志望校で、進学後受けられる配慮や、受験時に得られる特例措置などを、早めに調べておくことが大切です。
受験時に得られる特別措置には、次のような例があります。
受験時に得られる特別措置の例
- 別室受験(自閉症、高機能自閉症、SLD、アスペルガー症候群、ADHD等)
- 試験時間の延長(SLD)
- 集団面接を個人面接で実施(自閉症)
- 監督者による口述筆記(SLD)
- 前日に試験会場の下見(高機能自閉症)
- 保護者の別室待機(ADHD)
※()内の「自閉症・高機能自閉症・アスペルガー症候群」は、現在ではASDに該当。
こうした特例措置では、次の点に留意しましょう。
- 専門医から正式な診断が出ていない場合は、特例申請をすることが難しいため、まずは検査・診断を受ける。
- 申請は在籍中学校を通じて行い、教育委員会を介して手続きが進められるため、手続きに時間がかかる(申請の締め切りが受験の願書提出よりも早いことが多い)
特例申請をする場合は、現在在籍する学校にできるだけ早い段階で、相談しておくようにしましょう。(参考:鈴木慶太『親子で理解する発達障害 進学・就労準備の進め方』)
発達に特性がある中学生のお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)
発達障害の中学生のために家庭でできる対策

![]()
![]()
この章では、ASD・ADHD・SLDの種類別に対策を紹介するので、お子さんの特性にあわせて実践してみてください。
ただし何度も繰り返すとおり、お子さんのことを親だけ・ご家庭だけで抱え込まず、サポート団体などを利用することで、より適切・具体的な対策がわかります。(参考:本田秀夫『自閉症スペクトラム』、小池敏英・奥住秀之『これでわかる学習障がい』)
対策①ASD傾向が強い中学生
ASD傾向の強い中学生には、次の3つの対応が有効だと言われています。
- ①文字や図主体のコミュニケーションを取る
- ②家では静かな環境を整える
- ③休憩時間を意識する
- ①文字や図主体のコミュニケーションを取る
ASDの人の多くは、耳からの情報よりも、視覚的な情報の方が理解しやすいと言われています。
具体的には、「スケジュールは見やすい表にする」「やるべき課題などをリスト化する」などが効果的です。
- ②家では静かな環境を整える
ASDの人の中には「聴覚過敏」などの過敏症が併存する人が多いです。
そのため、特に受験期などは、学習環境を静かに保つための配慮が必要になります。
- ③休憩時間を意識する
「過集中」への対策です。特にASD傾向がある子どもは、過集中に入ると体力がなくなるまで徹底した集中状態になることがあります。
そのため、お子さんの様子を見て、適宜親御さんから休憩するように促すことが必要です。
対策②ADHD傾向が強い中学生
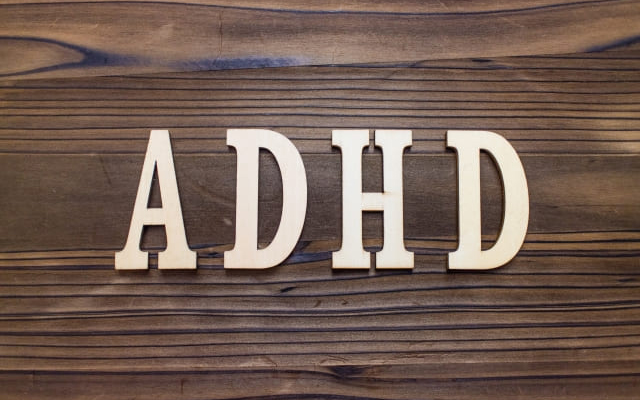
ADHD傾向の強い中学生には、次の2つの対応が有効だと言われています。
- ①机の上に必要なもの以外を置かない
- ②課題を小分けにしてその日にやるべきことを決める
- ①机の上に必要なもの以外を置かない
ADHDの「整理整頓が苦手」という特性・特徴への対策です。
机の上に必要な物のみを置くと決めれば、物が散らかりづらく、勉強に集中しやすいくなります。
- ②課題を小分けにしてその日にやるべきことを決める
ADHD傾向の強い中学生は、課題は漠然と捉えられていても、するべきことを細分化できず、ゴールまでの道筋を立てられないことがあります。
そのため、親御さんが「今日はここまでやろう」と声かけをして、道筋を立てる手助けをすることが有効です。
また、少し手間はかかりますが、その日に進める分の課題だけを印刷して渡すと、集中して取り組みやすくなるでしょう。
対策③SLD傾向が強い中学生
SLD傾向のある中学生には、次の2つの対応が有効です。
- ①特性にあわせて理解の仕方を変える
- ②可能なら電子機器などのツールを利用する
- ①特性にあわせて勉強方法を変える
SLDのうち、読字障害の傾向がある中学生には、「文章を目で見て読むと理解しづらいけれど、音声で聞くとスムーズに理解できる」といった特性をもつお子さんもいます。
そのような場合は、苦手な媒体での勉強ではなく、得意とする媒体での勉強方法を探しましょう。
- ②電子機器などのツールを利用する
「電子機器などのツールに頼る」ことも有効です。
例えば、書字障害の傾向がある子は、板書をノートに書き写すのに時間がかかります。
文字を手書きせず、タブレットでの写真撮影や文字入力に変更すれば、困り事の緩和が期待できるのです。
周りの子の目もあるため難しいかもしれませんが、担任の先生や学校側に相談してみる価値はあるでしょう。
発達に特性がある中学生のお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)
発達障害の中学生と不登校の関係性

発達障害の中学生の中には、発達障害の特性や特徴に関連して、学校での人間関係や勉強に苦労することで、不登校になる中学生もいます。
また、心の調子を崩して不登校になり病院へ行ったところ、発達障害であることが初めてわかることもあるのです。
いずれの場合も、発達障害の子どもが不登校になった際は、次の対応方法を実践してみてください。
- まずは「休んでもいい」「無理をしなくてもいい」と伝える
- 子どものペースにあわせて話や困り事に丁寧に耳を傾ける
- ねぎらいや苦労に理解を示すような言葉を掛ける
- 専門家のアドバイスを受けながら、まずは体調を治す
不登校も発達障害と同じく、公民を問わずサポート団体を利用することが大切です(私たちキズキでは、不登校と発達障害の両方の相談が可能です)。
不登校のサポート団体は、「(お住まいの地域名)+不登校+相談」などとインターネットで検索すると見つかるでしょう。
お子さんはもちろんですが、親御さんにも合いそうな団体を見つけて、相談してみてください。
親御さんも「自分の時間」をつくってリフレッシュすることを心掛けてみてください。
![]()
まとめ:発達障害の中学生の子に対して親ができることは、たくさんあります

![]()
![]()
![]()
■発達障害の中学生をサポートする上で大切なこと
- 担任の教師や学校や支援団体などとサポート体制を築く
- 親御さん自身が発達障害の理解を深めて受けいれる
- 発達障害に対応した家庭教師や学習塾も利用できる
- 不登校になったときは無理に通学させようとしない
この記事が、お子さんと親であるあなたのお役に立ちましたら幸いです。
さて、私たち、キズキは、発達障害や不登校のお子さんのための塾&家庭教師です。
13年間で3,000名以上、発達障害や不登校のお子さん・親御さんをサポートしてまいりました。
不登校に関する無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。
少しでも気になる方は、お気軽にご連絡ください。
発達に特性がある中学生のお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

監修:安田祐輔
やすだ・ゆうすけ。発達障害(ASD/ADHD)によるいじめ、転校、一家離散などを経て、不登校・偏差値30から学び直して20歳で国際基督教大学(ICU)入学。卒業後は新卒で総合商社へ入社するも、発達障害の特性も関連して、うつ病になり退職。その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。経歴や年齢を問わず、「もう一度勉強したい人」のために、完全個別指導を行う。また、不登校の子どものための家庭教師「キズキ家学」、発達障害やうつ病の方々のための「キズキビジネスカレッジ」も運営。
【新著紹介】
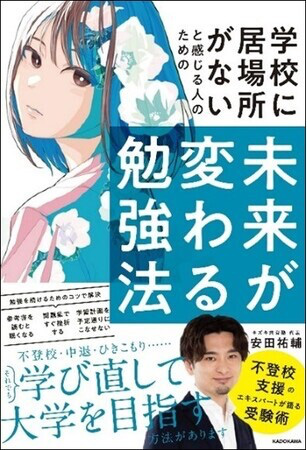
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法』
(2022年9月、KADOKAWA)
Amazon
KADOKAWA公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【著書など(一部)】
『暗闇でも走る(講談社)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』)
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

共同監修:半村進
はんむら・すすむ。1982年、茨城県生まれ。東京大学文学部卒。
小学校時代から転校を繰り返し、運動ができないこと、アトピー性皮膚炎、独特の体形などから、いじめの対象になったり、学校に行きづらくなっていたことも。大学に入学してようやく安心できるかと思ったが、病気やメンタルの不調もあり、5年半ほど引きこもり生活を送る。30歳で「初めてのアルバイト」としてキズキ共育塾の講師となり、英語・世界史・国語などを担当。現在はキズキの社員として、不登校・引きこもり・中退・発達障害・社会人などの学び直し・進路・生活改善などについて、総計1,000名以上からの相談を実施。
