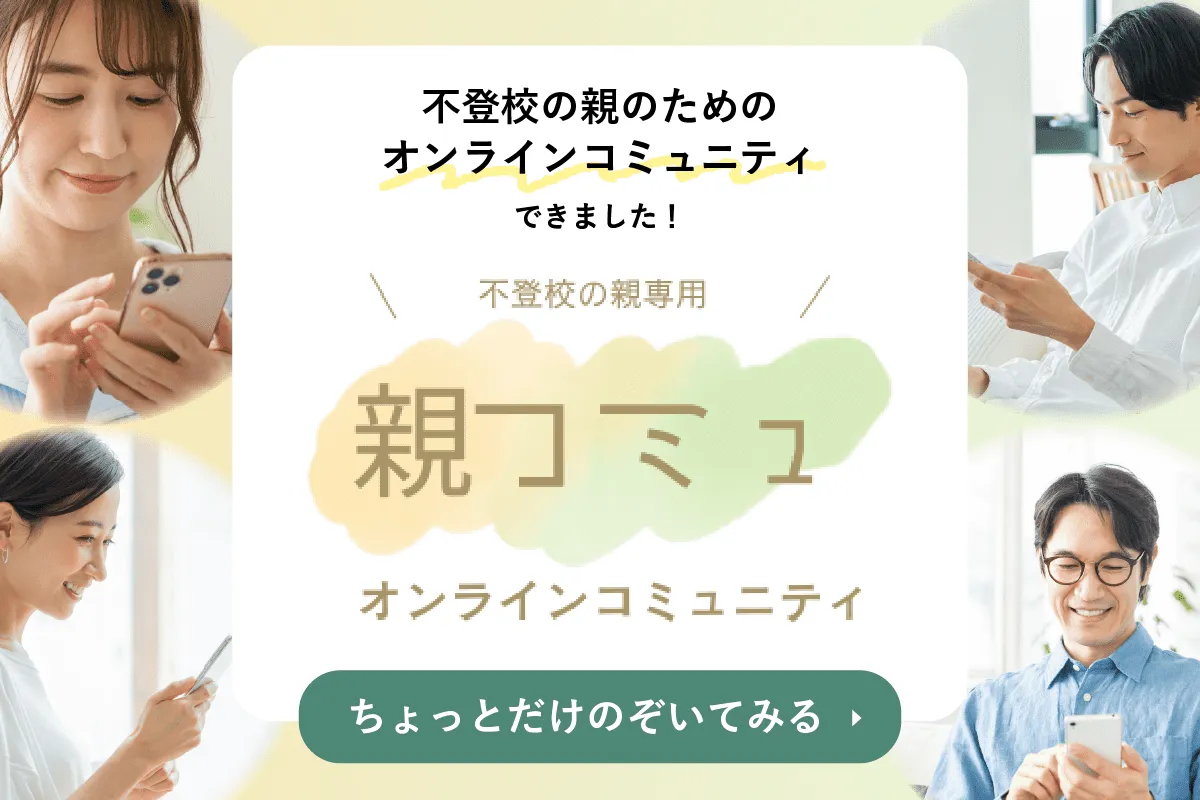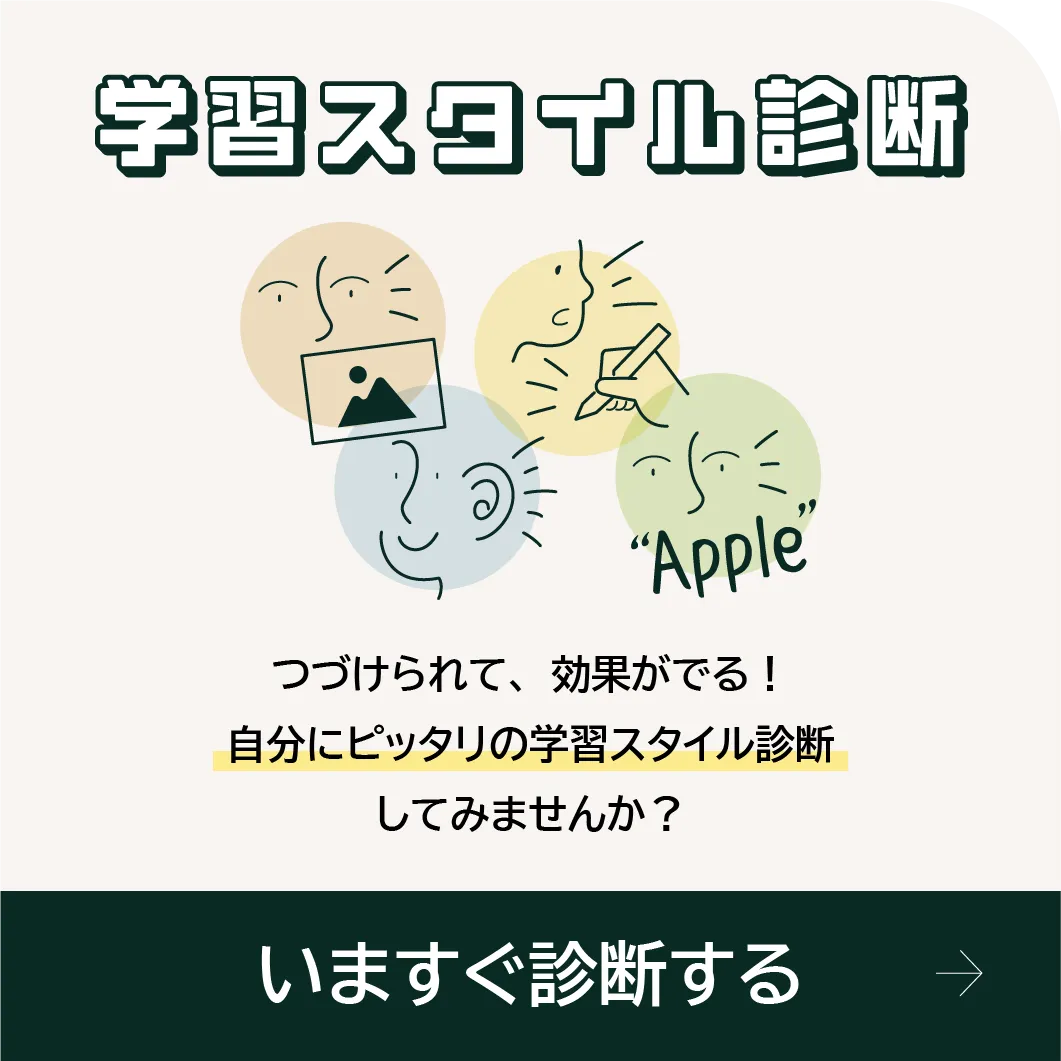不登校からの高校受験はどうなる?焦らないための高校受験の考え方

![]()
![]()
中学生のお子さんが不登校だと、「高校受験は難しいかも…」「公立高校に行けないかも…」と不安に感じることがあるかもしれません。
しかし、心配は無用です。中学で不登校だったとしても高校受験に成功し進学する人は多くいます。
ただし、不登校から高校受験を成功させるためには、焦らないことが大切です。そして、内申点や欠席日数などいくつかの注意点を踏まえたうえでの高校選び、対策などが必要になります。
このコラムでは、不登校のお子さんが高校受験を目指すときの注意点や、高校選びのコツを徹底解説します。
また、不登校でも行ける全日制高校も紹介します。
不登校の子どもの高校受験で悩んでいる親御さんは、ぜひ参考にしてください。
目次
不登校からの高校受験では「調査書」に注意

![]()
![]()
「調査書」とは、中学校の先生が作成する「生徒の学校生活の態度と成績を書いた文書」のことです。
調査書のうち、教科の成績を得点化した項目を「内申点」と言います。
一般的に、不登校だと、次の理由から内申点が低い可能性があります。
- 学校の勉強から離れている
- 授業に出席していない
- 定期テストを受けておらず点数がない
- 定期テストを受けていても点数が低い
- 欠席日数が多い
補足
- 調査書や内申点では、「中学校3年間」の生活や成績が書かれる場合もあれば、「3年生のみ」である場合もあります
- 出席日数のほか、英検などの資格取得や作文コンクールなどの受賞歴も記入されます
- 調査書や内申点の付け方は、都道府県や地域によって異なります
調査書①調査書は合否に関係することがある
![]()
![]()
必ずではありませんが、公立高校の受験では提出することが多いです。
東京都の全日制公立高校の「学力検査に基づく入試」では、学力試験と調査書の内容を「7:3」や「6:4」で配分しています。(参考:東京都教育委員会※PDF『調査書点の点数化について』)
※学力試験や調査書以外にも、作文や面接などが実施・審査されることもあります。
※内申点(調査書)の点数配分は、都道府県・高校・学科・受験方法などによって異なります。
調査書②教室に通わず出席日数を増やす方法がある

不登校で教室に通えなくても、出席日数を増やす方法はあります。
例
- 保健室登校(別室登校)
- フリースクールや学習塾への「登校」
- 適応指導教室(教育支援センター)への「登校」
- オンライン教材を用いた自宅学習
その名前のとおり、「学校には行くけれど、教室ではなくて保健室(別室)に登校する」ことです。利用できるかどうかは、在籍している中学校の先生に確認しましょう。
コラム「保健室登校とは?|意味・メリット・不登校との関係・教室復帰の方法」では、保健室登校についてさらに詳しく解説しているので、気になる方は是非参考にしてください。
不登校のお子さんが学校の代わりに通える民間の施設です。中学校の校長先生が認めれば、フリースクールや学習塾への「出席」を「学校への出席」とみなされます。お子さんに合いそうな施設があるかは、インターネット検索で探せます。
不登校のお子さんが学校の代わりに通える公的な施設です。フリースクールとは異なり、「元の学校・教室への登校再開」も目的としています。利用の可否は、中学校の先生に確認してみましょう。
2019年に文部科学省より出された『不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて』で、一定の条件を満たすことができれば、自宅でのオンライン学習が出席扱いとされるようになりました。(参考:文部科学省※PDF「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」)
調査書③高校受験前に確認すべきポイント
不登校からの高校受験にあたっては、次の点を確認することが大切です。
また、お子さんご本人や親御さんだけでの確認は難しいことも多いため、中学校や塾、家庭教師、不登校のサポート団体などに相談しましょう。
確認ポイント
- 志望校の受験で、調査書の提出が必要か
- 調査書の提出が必要なら、それが合否にどのくらい(何点くらい)関わるのか
- お住まいの都道府県では、どういう基準で内申点(調査書)を付けているか
不登校状態にあり高校受験が不安なあなたのための塾&家庭教師【キズキ】相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)
詳しく見る不登校で欠席日数が多い場合の高校受験の考え方

![]()
![]()
高校受験の際に、調査書の提出が必要ない高校もあります。
ここからは、公立と私立に分けて、詳しくお伝えします。
①不登校から公立高校への受験を考えている場合
公立高校では、一般的に「欠席日数の多い生徒は審議の対象とする」としています。
「審議の対象とする」とは、簡単に言うと「合格が難しくなる」ということです。
「3年間の欠席日数が○○日を超える生徒は審議の対象とする」など、日数の基準が高校によって定められています。
とは言え、「不合格とする」のではなく、あくまで「審議の対象とする」なので、審議の結果合格になることもあるのです。
審議の対象となる例
- 「1・2年生のときは休みがちだったけど、3年生のときは問題なく出席できた」
- 「ケガで長期入院をしていたせいで、やむをえず欠席日数が多くなった」
このように、「中学校では欠席が多かったけれど、高校では問題なく出席できそうな場合」などは、中学校の先生がその旨を調査書に「特記事項」として記入することがあります。
![]()
また、都立高校などでは、「自己申告書」を提出し、欠席した事情を説明できます(「自己申告書」の有無は、都道府県や地域によって異なります。「不登校からの高校受験で役立つ「不登校枠」」の章で改めてお伝えします)。
ほかにも、チャレンジスクール(東京都立)のように「不登校経験のある生徒」を積極的に募集している高校や、通信制高校、定時制高校など、中学の成績・出席日数をほぼ審査しない公立高校もあります。
つまり、「不登校だから公立高校にいけない」というわけではないのです。
②不登校から私立高校への受験を考えている場合
![]()
![]()
調査書の内容が不安なら受験する高校を、「調査書の提出が必要ではない学校」にするのも一つの方法です。
学力試験の結果だけで合否を判断する受験形式は、「オープン型入試」と言われています。
また、欠席日数や成績をほぼ審査しない、私立の通信制高校もあります。
このように、中学の時に不登校で欠席日数が多いからと言って、「高校に行けない」」ことはないのです。
不登校からの高校受験で役立つ「高校の種類・特徴」

![]()
この章では、不登校から受験を目指す人が知っておきたい高校の種類と特徴をお伝えします。
下記の表を適宜確認しながら、順に解説していきます。
| 全日制 | 通信制 | 定時制 | チャレンジスクールなど | |
|---|---|---|---|---|
| 入試 | 学力試験+調査書 ※私立は調査書不要の場合も |
書類審査+面接が多い | 学力試験+面接 ※ただし学力はあまり考慮されないことが多い |
志願申告書+作文+面接 |
| 制度 | 学年制が多い | 基本は単位制 | 学年制と単位制がある | 基本は単位制 |
| 登校頻度 | 毎日(朝~夕方) | 基本は指定のスクーリング日のみ | 平日毎日(夕方~夜が多い) | 平日毎日(時間の枠を選択) |
| 卒業年数 | 3年 | 最短で3年 | 3〜4年 | 3〜4年 |
| 授業難易度 | 学校によって異なる | 通常はやさしい | 通常はやさしい | 通常はやさしい |
「学年制」とは、中学までと同じように、1年生・2年生・3年生と「学年が存在する仕組み」のことです。
学年制の学校では、学校が定めた時間割に従って授業を受けます。
「単位制」とは、「その年に受ける授業を自分で決められる仕組み」です。
単位制の高校には、学年の概念(クラスメイト全員に共通の時間割)がありません。
全ての高校に共通して、高校の仕組みに関わらず、「お子さんが通いやすいか」「卒業後の進路はどうか」など、相性を確かめることが大切です。
そのため、事前に気になる高校の情報を積極的に集めましょう。
事前に高校の情報を集める方法
- 見学や説明会に参加する
- 資料請求する
- 中学校と相談する
- 塾・家庭教師などと相談する
高校①全日制高校:不登校でも行ける全日制高校とは?
「全日制高校」とは、高校と聞いて一般にイメージされる、「平日は毎日登校して、朝から夕方まで授業を受ける高校」のことです。
さきほどもお伝えした通り、不登校からでも行ける全日制の公立高校はあります。
ただ、私立高校の受験審査の基準は、学校によって様々なので、私立高校の方が合格しやすい場合もあります。
私立高校の合格基準の例
- 入学試験の点数だけで合否を決める(内申点を見ない)
- 内申点よりも入学試験の点数を大きく重視して合否を決める
- 不登校のために内申点が低くても、事情を配慮する
![]()
キズキにも、中学校で不登校の状態から、半年程度の受験対策で私立高校に合格した生徒さんは数多くいます。
全日制高校の特徴は、コラム「不登校からの全日制高校進学|6つのポイント・学校の選び方・実例も」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
高校②通信制高校
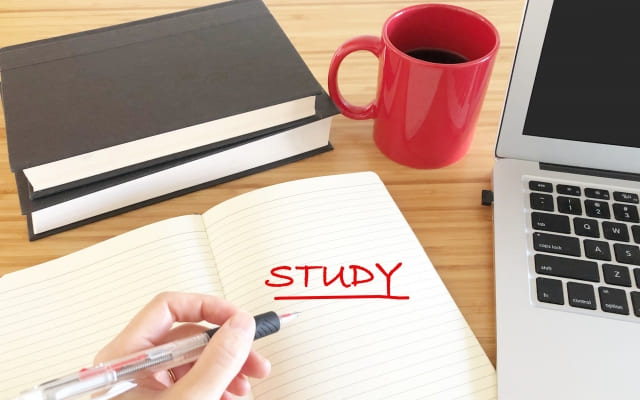
通信制高校も、不登校からの高校受験を目指す人から支持されている進学先の一つです。
通信制高校とは、郵便やe-mail、オンライン学習サイトなどを用いた、自宅学習がメインになる高校です。
通信制高校の特徴
- 毎日の登校が必要なく、学校が定めた日にだけ登校する(これを「スクーリング」と言います)
- 勉強は、主には学校から送られてくる教材を利用して、自宅で行う
- スクーリングや、修学旅行などのイベントの頻度は、学校によって大きく異なる
- 入学試験は、筆記試験ではなく、面接や作文だけのところが多い
- 中学校や高校で不登校になった人を積極的に受け入れている学校が多い
通信制高校の受験では、不登校の経験そのものが不利になることはありません。
![]()
その場合、「大学受験用の勉強」は家庭教師や学習塾で行うことを検討しましょう。
通信制高校は、コラム「通信制高校とは?特徴・メリット・選び方・オススメの高校などをご紹介」で、さらに詳しく解説しています。
高校③定時制高校
定時制高校も候補の一つです。
定時制高校(単位制高校)も、通信制高校同様に、不登校経験者や全日制高校からの転入生、社会人など、様々な人を受け入れています。
定時制高校の特徴
- 平日は毎日登校して授業を受ける
- 授業の時間帯は、昼から夜にかけてのことが多い(最近では、朝から授業を行う高校もある)
- 3年で卒業できる高校もあれば、4年で卒業するスケジュールになっている高校もある
「夜学(やがく)」や「夜間高校」などの名前でも親しまれています。
卒業までに必要な年数は学校ごとに異なるので、受験を考える段階で学校ごとの情報をよく調べましょう。
![]()
定時制高校と通信制高校のどちらに進学するか迷ったとき、こうした人との交流が多いかどうかが一つの判断基準になるかもしれません。
コラム「定時制高校ってどんなところ?(1)定時制高校の基本情報」では、定時制高校についてさらに詳しく解説しています。
高校④チャレンジスクールなど

チャレンジスクールのような高校も、受験の候補の一つになるでしょう。
チャレンジスクールとは、「単位制かつ定時制の東京都立高校」で、「中学校や高校で不登校や中退を経験した生徒のための学校」です。
チャレンジスクールの特徴
- 入学試験に筆記試験はなく、面接と作文、志願申告書などで審査。
- 公立高校でありながら、内申点(調査書)は考慮されない。
- 都立高校なので、一般的な私立高校と比べると学費を抑えられる。
- 授業は午前、午後、夜間の3部に分かれていて、自分の生活リズムに合わせて勉強する時間を選べる。
このような特徴から、不登校経験のある受験生の志望校の一つとして知られています。
なお、チャレンジスクールは東京都にあるため、東京から遠くにお住まいの場合は現実的な選択肢ではないかもしれません。
ですが、今後都内へ引っ越す可能性がある場合には、入学・転校の選択肢になります。
また、東京都にお住みでなければ、お住まいの地域にチャレンジスクールと類似した学校や制度がないか調べてみましょう。
- 神奈川県の例:クリエイティブスクール
- 大阪府の例:エンパワーメントスクール
不登校からの高校受験で役立つ「不登校枠」
![]()
![]()
一般的に、公立高校の一般入試では、「学力試験のテスト」と「調査書点(内申点)」が審査されます。
不登校だと(=欠席日数が多いと)、調査書点が低くなり、不合格になる確率が上がることがあります。
不登校枠の場合、欠席が多い理由を説明することで、不合格の確率を下げる(合格の確率を上げる)ことができるのです。
(なお、勘違いされがちですが、不登校枠は、「不登校の子どものために特別に設けられた応募枠(合格者枠)」のことではありません。)
以下、詳しくお伝えします。
不登校とは?
![]()
文部科学省では、「不登校」の定義を次のように定めています。
「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いた者」
つまり、我が子が不登校だと思っていても、年間の欠席日数が29日以下であったり、欠席の理由が病気であったりする場合は、定義上では不登校ではないのです。
不登校枠とは、不登校の子どもに対して「特別な配慮」がなされる選抜方法
不登校枠とは、不登校の子どもに対して「特別な配慮」がなされる選抜方法の俗称です。
「枠」と聞くと、不登校の子どもが優先的に応募・合格できるかのように思われますが、そういった優遇措置ではありません。
また、この制度は国が行うものではなく、都道府県が独自で行っているものです。そのため、お住まいの地域での制度を詳しく調べてきましょう。
参考として、「不登校枠」と言われている制度の実際の例を紹介します。
■東京都
調査書に記載された欠席日数について、欠席の事情を説明する必要がある場合など、都立高校に理解してほしい事情を説明する必要がある場合、志願者は、自己申告書(様式13)を志願する都立高校の校長に提出することができる。 なお、自己申告書は、志願者及び保護者が記入し、厳封して入学願書等の出願書類とともに志願する都立高校の校長に提出する。
■神奈川県
神奈川県公立高校の入学者選抜では、特別の事情により長期欠席が合った志願者につつきましては、志願者の申請により、「資料の整わない者」の取扱いになります。
「資料の整わない者」としての扱い
選考に当たり、調査書の各教科の学習の記録欄の記載内容については、申請者の「希望する取扱い」にも続いて扱い、総合的な選考をします。
■愛知県
Q 欠席日数が多いのですが、特別な配慮はありますか?
A 中学校の第2学年、第3学年のいずれか又は両方の学年における欠席日数が、年間30日程度以上の入学志願者のうち希望する人は、全ての選抜で「自己申告書A」を提出することができます。
また、中学校卒業見込者で、やむを得ない事情により、第3学年の欠席日数が出席すべき日数の半分以上である人は、一般選抜において「長期欠席者等にかかる選抜方法」の適用を中学校を通じて申請することができます。
カンタンにまとめると、次のようになります。
ポイント
- 欠席日数が多い場合、自己申告書で欠席理由を説明でき、選考時に配慮がなされる(欠席日数が多いことによる不合格の確率を下げる(合格の確率を上げる))。
ただし、配慮がどの程度なされるかは、詳しく明言されていません。また、「配慮してもらえるから必ず合格できる」ものではないのです。
そのため、受験当日に合格圏内に入れるだけの点数を獲得できるように、受験勉強をしておきましょう。
制度の詳細は、都道府県によって異なります。お住いの自治体の教育委員会のウェブサイトをチェックしてください。
不登校からの高校受験で役立つ「高校選びのコツ」
![]()
不登校の受験生が高校を選ぶときに大切なコツを、3つお伝えします。
コツ①不登校の指導実績がある家庭教師などに相談する

![]()
不登校からの高校受験に詳しい家庭教師・学習塾・サポート団体などはたくさんあります(私たちキズキもその一つです)。
不登校の指導実績がある家庭教師や学習塾などでは、中学校以上にきめ細やかなサポートやアドバイスを得られます。
そのため、学力に不安があり独学での高校受験が心配な人にもオススメです。
家庭教師などを探したい場合は、インターネットで「不登校+高校受験+相談+お住まいの市区町村名」などと検索しましょう。
コツ②学校見学会に参加する
![]()
校風や学校の雰囲気は各高校で大きく異なります。また、進学や就職に関する実績やサポート体制にも異なる部分がが多いです。
学校見学会や説明会に参加することで、実際の学校の様子や通学環境を確認できたり、進路などの気になることを質問できたりします。
お子さんの参加が難しそうな場合は、ご本人の希望を聞きつつ、親御さんだけでも参加してみましょう。
時期的に説明会が終わっている場合は、高校のウェブサイトをよく見たり、電話やメールなどで個別に質問したりすることがオススメです。
コツ③不登校の親の会・サポート団体に相談する
親の会や不登校のサポートを行う団体などに相談してみるもの一つの方法です。
親の会とは、不登校や発達障害などの子どもの親が集まり交流を行う会。各会によって、行われることは様々ですが、親同士の情報交換や相談、専門家を招いてのセミナーなどを開催しています。各都道府県や市町村などの地域に分かれて活動していることが多いです。
親の会では、不登校のお子さんを持つ親御さんが集まっているため、すでに受験を経験した人に話を聞けるはずです。
また、同じ年のお子さんを持つ親御さんと出会えれば、受験に対する疑問や不安などを共有できることもあるでしょう。
不登校のサポート団体では、不登校のお子さんの生活や勉強、進路の相談ができます。
また、必要であれば支援を受けることも可能です。(私たちキズキでも、無料相談を行っています)
サポート団体には、公的団体と民間団体があり、公的団体はお住いの自治体の相談窓口から問い合わせられます。
また、こういったサポート団体には、不登校に関する知識が豊富な専門家が在籍していることも多いため、お子さんの進路選択に役立つアドバイスをもらえるでしょう。
コツ④信頼できる中学校の先生などと相談する
![]()
中学校の先生は、基本的な公立・私立高校などの知識だけでなく、不登校の生徒さんにあった進路や受験先をたくさん知っています。
さらに、お子さんの欠席日数や内申点、学力なども理解しています。そのため、お子さんに適した進路や受験先など、具体的なアドバイスを聞けるはずです。
相談の場にはお子さんも加わった方がよいですが、難しい場合は親御さんだけでもご相談することをオススメします。
コラム「不登校からの高校進学|進学しやすい高校・高校選びのポイントを解説」では、中学校で不登校だった人が進学しやすい高校4種類を紹介しています。
【タイプ別】不登校からの高校受験で役立つ「高校の選び方」

![]()
![]()
不登校のタイプごとにアドバイスをお伝えするので、お子さんの状況に近いものを参考にしてください。
いずれの不登校のタイプも、親子だけで悩まず、学校の先生、家庭教師や塾の先生、不登校のサポート団体などに相談することが大切です。
タイプ①今、中1・中2から不登校で高校受験を目指す場合
![]()
- 調査書を重視しない高校・受験方式を探す
- 3年生での出席日数(内申点)を上げながら、3年生のときの調査書だけを審査する高校を探す
- 3年生での出席日数(内申点)を上げながら、1・2年生時の不登校について調査書で「説明」できそうなら、調査書を審査する高校も視野に入れる
ここで言う「内申点を上げる」というのは、「無理にでも学校に行こう」ということではありません。
保健室登校やフリースクールへの出席などで登校日数(内申点)を上げる手段もあるのです。
ほかにも、資格取得や、作文コンクールなどの受賞も、内申点にプラスに働く可能性があります。
![]()
![]()
お子さんの心身の調子を崩さないように気をつけながら、できることがないか、担任の先生などに相談してみましょう。
タイプ②今、中学3年生で不登校の場合
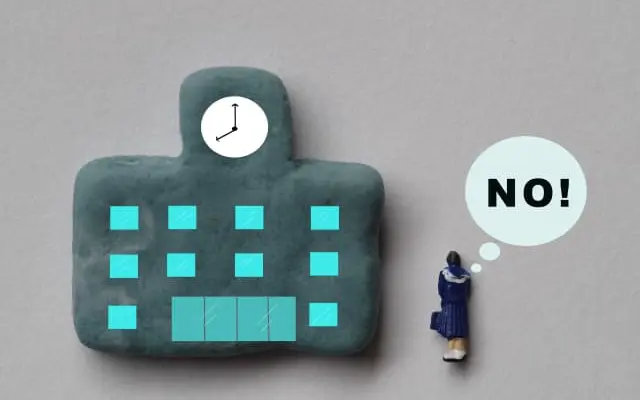
![]()
- 調査書を重視しない高校・受験方式を探す
- これから内申点を上げられそうなら、調査書を審査する高校も視野に入れる
前にも述べたように、私立高校などは、受験時に調査書を考慮せずに、学力のみで合否を判断することが多いです。また、学力試験がない学校もあります。
一般的に内申書を重視しない高校
- 通信制高校
- 定時制高校
- チャレンジスクール
- 一部の私立高校
現在中学3年生のお子さんは、まず調査書を重視しない高校・受験方式を探すことがオススメです。
その上で、詳しい人にも相談しつつ、お子さんの状況や性格に合いそうな高校を探しましょう。
タイプ③小学校~中学校の現在まで不登校の場合
![]()
そういったお子さんは、次の点を意識して受験先を探しましょう。
- 現在の学力や調査書で入学できそうな高校・受験方式を探す
- 勉強が不安なら、家庭教師や塾などを利用する
- 体力が少なかったり生活が乱れていたりするなら、医者などを頼る
- 勉強や生活が上向いてきたら、候補を増やす
まずは、「現在のお子さん」の学力や調査書で進学できそうな高校・受験方式を探すことが大切です。
勉強から離れている場合や勉強が苦手な場合は、基礎学力の定着や高校受験・進学後のために、学び直しができる家庭教師や塾などを活用しましょう。
![]()
![]()
受験や入学の前から、少しずつ体力をつけたり昼夜逆転の生活を改めたりするところから始めましょう。
学力が向上したり、生活が整ったりしていくうちに、高校の選択肢が増えることもあります。
全日制にこだわりがなければ、通信制や定時制も視野に入れて検討してみることがオススメです。
タイプ④学校生活への不安から不登校になっている場合
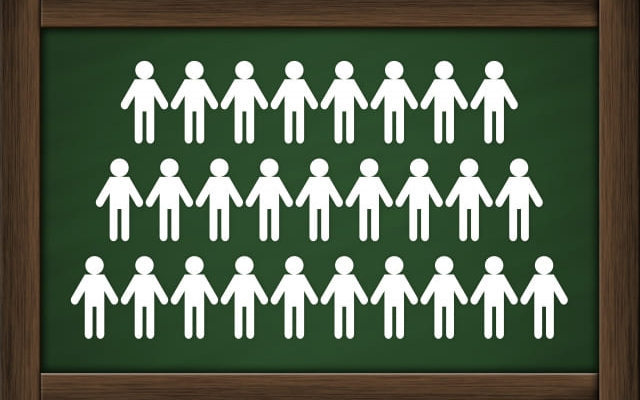
勉強面では問題なく高校受験に合格できそうでも、以下のように、学校生活(集団生活)に不安を覚えるお子さんもいるでしょう。
- 人の輪の中に入るのが怖い
- ひきこもり気味で、通学できるか不安
- 朝起きられないから、学校の授業に生活が合うか不安
- 気持ちや体調が不安定で、毎日通えるか不安
そんなお子さんに関しては、次のことに留意しましょう。
■ポイント
- 心身の調子や生活改善について、医者やカウンセラーに相談する
- 学力は塾・家庭教師を利用したり、学校に補習を頼んだりする
- コミュニケーションは、フリースクールや習い事教室などを利用する
- 受験や学校に行くことを怖いと本人が感じている可能性があるので、周囲がサポートする
- 「毎日の通学」や「朝からの授業」に不安があるようなら、通信制高校や定時制高校を視野に入れる
本人や家族の「努力」だけで改善させようとはせず、医師やカウンセラーに相談することが大切です。
タイプ⑤病欠による不登校が多い場合
![]()
![]()
病気は、何よりも医療機関からのアドバイスが必要になります。
その上で、登校自体が難しいのであれば、通信制高校がオススメです。
通信制高校であれば、自宅学習をメインに勉強を進められます。
不登校からの高校受験に関する「よくある質問と回答」
中学不登校からの高校進学について、キズキへのよくある質問と回答を紹介します。
回答は一般論です。私たちキズキにご相談いただければ、「実際のあなた(のお子さん)」のための、より具体的なお答えができると思います。
よくある質問①受験での審査
質問:調査書・出席日数・提出物・定期テストがどれくらい重視されますか?また、それぞれの点数や評価を上げるためにはどうしたらよいでしょうか?
どのくらい重視されるのかは、公立の場合は都道府県、私立の場合は学校によって異なります。
そのため、全員に共通した回答は難しいです。志望校が決まっているようでしたら、その学校の情報を集めましょう。
また、一般論として点数や評価を上げるためには、次のような方法があります。
- 出席日数は、フリースクールなどでの出席で代替できる方法を探す
- 課題提出では、学校に出された課題はもちろん、自主的に出せるもの(※)に積極的に取り組む(※学校が使っているものとは違う教材での勉強の実績、勉強関係の動画を見てまとめたもの、英検や漢検などの資格、公開講座に出た出席証明、芸術系のコンクールへの出展など)
- 定期テストは、別室受験や保健室受験を依頼して受ける
- 全てのテストを受けられなくても、1科目、初日と最後など、無理のない範囲で受けることも一つの方法
- 課外活動(部活動)に一生懸命取り組み、調査書に記載してもらう
よくある質問②公立高校への進学
質問:「このままだと公立高校には行けない」と中学校側に言われたのですが、どうすればよいですか?
公立高校であれば、「このままだと…」とは言われていても、先述の不登校枠(のような仕組み)を探すことで、進学できる可能性があります。
そのため、まずはお住まいの地域の教育委員会などが開催している進路相談会に行ったり、電話やメールで質問したりしましょう。地元の不登校サポート団体に話を聞くのも一つの方法です。
中学校側との連携も必須です。中学校側から進路希望票を出してほしいと言われた場合は、最終期限となる提出期限を聞いておき、その期限までに志望校を検討して提出しましょう。
よくある質問③特別な提出物
質問:「テストを受けてないから特別な提出物を出さないといけない」と言われました。どうすればよいですか?
一部の都道府県では、高校受験のために、定期テストの点数や模試の点数を高校にあらかじめ提出する慣行があります。
不登校に伴ってテスト・模試を受けていない場合は、過去に受けたものがあればその結果を提出しましょう。
また、過去に受けたものがなければ、今からでも受けられる試験や、通常提出するテスト・模試の代わりとなる試験がないかを聞いて受験しましょう。
そうすることで、お子さんが受かりやすい安全圏の学校を、中学校側から伝えてもらえます。
よくある質問④起立性調節障害
質問:起立性調節障害で起きられない状態です。本人は高校には進学したいと言っているのですが、大丈夫でしょうか?
大前提として、医師の意見を聞くことが必須です。その上で、中学3年生の年明けぐらいの時点で、「朝早く」ではなくとも、昼までには起きられるかが大きな節目になります。
起きられる場合は、そこから徐々に起きる時間を調整できるようになるでしょう。
起きられない場合は、定時制高校や通信制高校を積極的に視野に入れてよいかもしれません。
お子さんが言う「高校に行きたい」気持ちが、「毎日、朝から夕方まで行きたい」なのか、「週に何回か行きたい」なのかによって、志望する高校も変わってきます。
また、通学に必要な時間や、補習や小テストで早く登校する可能性があるかどうかも、高校選びの際に確認しましょう。
ほかにも、食生活ではカフェインをあまり取らないようにするなど、生活の中で気をつけられることにも積極的に取り組んでみてください。
コラム「起立性調節障害による不登校|症状や治療法・今後の進路・相談先を紹介」では、起立性調節障害について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
よくある質問⑤周囲が全日制高校しか認めない
質問:学校の先生や祖父母、叔父叔母、近所の人、適応指導教室の人など、周りの人たちが全日制高校しか認めてくれないのですが、どうしたらよいでしょうか?
身近な人たちだけではなく、自分の地域外の相談機関や団体を頼りましょう。
特に、「自分と同じような状況の人」と接した経験がありそうな相談先を見つけることが大切です。
相談先は、市区町村単位ではなく、都道府県単位や日本全体で探してみましょう。その方が広い視野で相談先を探せます。
相談をする際には、特に「自分と同じような状況から、全日制以外の高校に進学した事例」を聞いておくことが大事です。
事例があれば、これまで理解を得られなかった周りの人たちにも理解してもらえる可能性があります。
しかし、それでも説得が難しい場合もあるかもれません。
折り合いがつかない場合は、理解のありそうな親戚を頼ったり、黙って受験をして「そこだけ合格した」と言って通うなどの方法を検討してもよいでしょう。
よくある質問⑥高校の選択肢が少ない
質問:自分が住んでいる地方では、「不登校から進学できる高校」の選択肢が少ないです。その中でどう選択したらよいでしょうか?
スクーリングのときに通いやすいところに校舎がある通信制高校がオススメです。
また、合宿型のスクーリングが年に1〜2回ある通信制高校も選択肢となるでしょう。
ほかにも、本人が嫌でなければ、寮付きの高校に行く方法もあります。
ただし、寮の場合、環境や人間関係が合わないとつらくなることもあるので、高校生向けの下宿を使うことも検討するとよいでしょう。
また、大前提として「お子さんが高校生活に何を望んでいるか」が一番大切です。
高校で何を学びたいのか、何をしたいのか、何を得たいのかなどを考えた上で、選択しましょう。
よくある質問⑦高校の選択肢が多い
質問:自分が住んでいる地方では、通信制やチャレンジスクールなど、不登校から進学できる高校の選択肢が多です。その中で、どう選ぶのがよいのでしょうか?
選択肢が多い場合も、高校に何を求めるかが重要です。目的によって、選ぶ高校は変わってくるでしょう。
目的の例
- 学力をつけたい(大学に進学したい)
- 確実に卒業したい
- 交友関係を作りたい
- できるだけ通う回数を増やしたい
- バイトなどの学外活動と両立したい
高校に通う目的を、お子さんにゼロから聞いても、答えにくい場合があります。
しかし、上記のような選択肢を示すと答えやすくなり、お子さんの希望が見えてきます。そして、希望がわかれば志望校も見えてきます。
それでも候補が多い場合は、通いやすさが重要になります。
通いやすさも変わらないなら、実際に見学に行き、雰囲気を見てみるのがよいでしょう。
また、単位の取得方法や成績の付け方、テストの受け方・回数などで比較することで、より希望に合った学校が見つかることもあります。
ほかにも、制服のデザインや学校周辺の町の雰囲気など、様々な部分に目を向けましょう。
また、親御さんの観点としては、同じように魅力がある候補が複数あるなら、学費で選んでもよいかもしれません。
よくある質問⑧全日制高校への進学
質問:本人は全日制高校への進学を望んでいますが、中学校に行けていない状態です。全日制高校の受験は認めてもらえるでしょうか?また、受験して受かるでしょうか?
まず押さえておきたいのが、学校に行けていない状態がどう受験に影響するかは、地域によって異なるということです。
お住まいの地域で評価される調査書が中2や中3からで、お子さんがまだその年齢でないのであれば、今から盛り返すことはできるでしょう。
また、3年間ぶんが評価される地域であっても、今は「不登校枠」がある場合もあるので、そちらを使って受験する方法も一つです。
私立であれば、模擬試験を受けておいて、その成績がよい場合は、個別に相談する方法もあります。または、調査書をあまり重視しない(審査しない)高校を選んでもよいでしょう。
成績がそれほどよくない場合は、熱意を見せる方法があります。
たとえば、志望校の説明会に何回も足を運んだり、その説明会で「この高校を受けたい」気持ちを伝えたりするなどです。
また、高校側から「学校に行けていなかったとしても続いたものがあるか」と聞かれることがあります。
そんなときのために、習い事やスポーツ、興味があることに関する勉強など、続いたものを作っておくと、よい印象に繋がるかもしれません(ただし、「受験のために」と思い詰めないようにしましょう)。
ほかにも、不登校専門の家庭教師や塾、地域の不登校の親の会、不登校からの受験に詳しい団体など、情報が集まっているところに相談してみるのもよいでしょう。
ただし、定時制高校、通信制高校、高等専修学校なども、見てみるとお子さんに合うところはあるかもしれません。そのため、全日制高校に絞り込み過ぎるのはやめましょう。
また、お子さんは、全日制そのものにこだわっているのではなく、「多くの人が行くところから外れたところに行きたくない」ために全日制高校を希望している場合もあります。
【親御さんの声】不登校への支援に関する実例
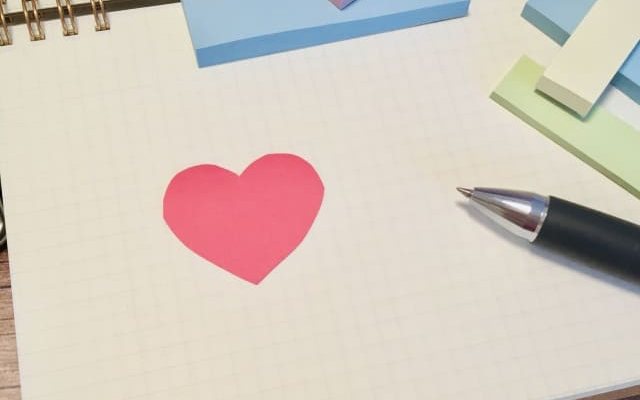
私たちキズキの生徒さんにも、不登校の中学生がたくさんいます。
参考として、親御さんの声を一つご紹介します。
この生徒さんはまだ高校受験の年齢ではありませんが、「中学校で不登校になったお子さんは、次の一歩に必ず進める」というお話としてご覧ください。
娘は、中学校に入学してすぐに、クラスメイトとのトラブルがきっかけで不登校になりました。
自宅では好きなことをして過ごしていて、外出もできていたのですが、学校には行けずどうしたらいいのか悩んでキズキ(家庭教師キズキ家学)を利用し始めました。
はじめは、教育コンサルタント(カウンセラー)の訪問支援でした。
訪問開始直後の娘は、知らない人が家に来ることに不安を見せていましたが、教育コンサルタントさんが娘の好きなことに一緒に取り組み、不安を解消してくれました。
また、娘の心理検査や知能検査を行ったことで、親の私も娘のことを客観的に理解できるようになり、娘への適切な接し方がわかるようになりました。
次に、スタディパートナー(家庭教師)のNさんにも訪問してもらうようにしました。
訪問開始からしばらくは、娘と私とNさんの3人で交流を深めて、新たに信頼関係を築いてくれました。
次第に娘とNさんだけの交流も可能になり、簡単な内容から勉強を再開しました。
娘は、Nさんとの授業を通して少しずつコミュニケーションと勉強に自信を持つようになり、慣らし登校や学校の先生との面談にチャレンジできるようになりました。
中2の今では、ほぼ毎日登校して部活にも参加しています。
授業の復習や宿題に取り組むなど、学習習慣も身につきました。
あせってばかりいた私に取って、教育コンサルタントとスタディパートナー(家庭教師)の訪問がどれほど心の支えになったかわかりません。
【関連動画】不登校経験を高校受験の面接で活かすためのポイント
こちらの動画(Youtube)「高校受験の面接で、不登校経験をどう語る?3つの対策で合格が近づきます!」では、このコラムの内容に関連して、面接のある高校受験の際に不登校の経験をどう話せばいいかをお伝えしています。
ポイントは、次の3つです。
- ①不登校経験をなかったことにはしない
- ②不登校には色々な語り方がある
- ③一人きりで考えなくてもいい
ご興味がありましたら、ぜひ参考にしてください。
まとめ:不登校からの高校受験でも合格できます

![]()
![]()
今回のまとめ
- 高校受験に調査書(内申点)や欠席日数が関わるのは事実だが、それで合否の全てが決まるわけではない
- 高校受験の仕組みや学校の種類を知ることが大切
- 高校の種類次第で、高校受験を成功させることは充分可能
- 不登校からの高校受験に詳しい人に相談することが大切
このコラムが、不登校からの高校受験を考えているお子さんと、親であるあなたのお役に立ったなら幸いです。
さて、私たち、キズキは、不登校のお子さんのための塾&家庭教師です。
13年間で3,000名以上、不登校のお子さん・親御さんをサポートしてまいりました。
不登校に関する無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。
少しでも気になったなら、お気軽にご連絡ください。

監修:安田祐輔
やすだ・ゆうすけ。発達障害(ASD/ADHD)によるいじめ、転校、一家離散などを経て、不登校・偏差値30から学び直して20歳で国際基督教大学(ICU)入学。卒業後は新卒で総合商社へ入社するも、発達障害の特性も関連して、うつ病になり退職。その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。経歴や年齢を問わず、「もう一度勉強したい人」のために、完全個別指導を行う。また、不登校の子どものための家庭教師「キズキ家学」、発達障害やうつ病の方々のための「キズキビジネスカレッジ」も運営。
【新著紹介】
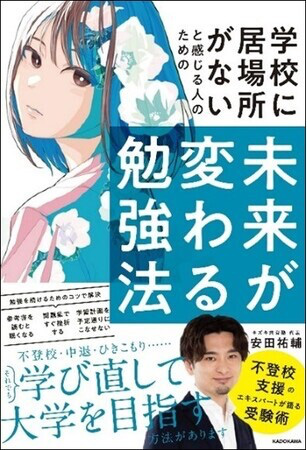
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法』
(2022年9月、KADOKAWA)
Amazon
KADOKAWA公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【著書など(一部)】
『暗闇でも走る(講談社)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』)
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

共同監修:半村進
はんむら・すすむ。1982年、茨城県生まれ。東京大学文学部卒。
小学校時代から転校を繰り返し、運動ができないこと、アトピー性皮膚炎、独特の体形などから、いじめの対象になったり、学校に行きづらくなっていたことも。大学に入学してようやく安心できるかと思ったが、病気やメンタルの不調もあり、5年半ほど引きこもり生活を送る。30歳で「初めてのアルバイト」としてキズキ共育塾の講師となり、英語・世界史・国語などを担当。現在はキズキの社員として、不登校・引きこもり・中退・発達障害・社会人などの学び直し・進路・生活改善などについて、総計1,000名以上からの相談を実施。
電話で相談・問い合わせ専門スタッフが丁寧に対応させていただきます!
0120-501-858フリーダイヤル受付時間:
月〜土曜・10〜20時
上記受付時間以外にも、着信をいただければ、必ず折り返しご連絡します(電話番号非通知を除きます)。また、留守番電話にメッセージを残していただくことも可能です。日時を問わずお気軽にお電話ください