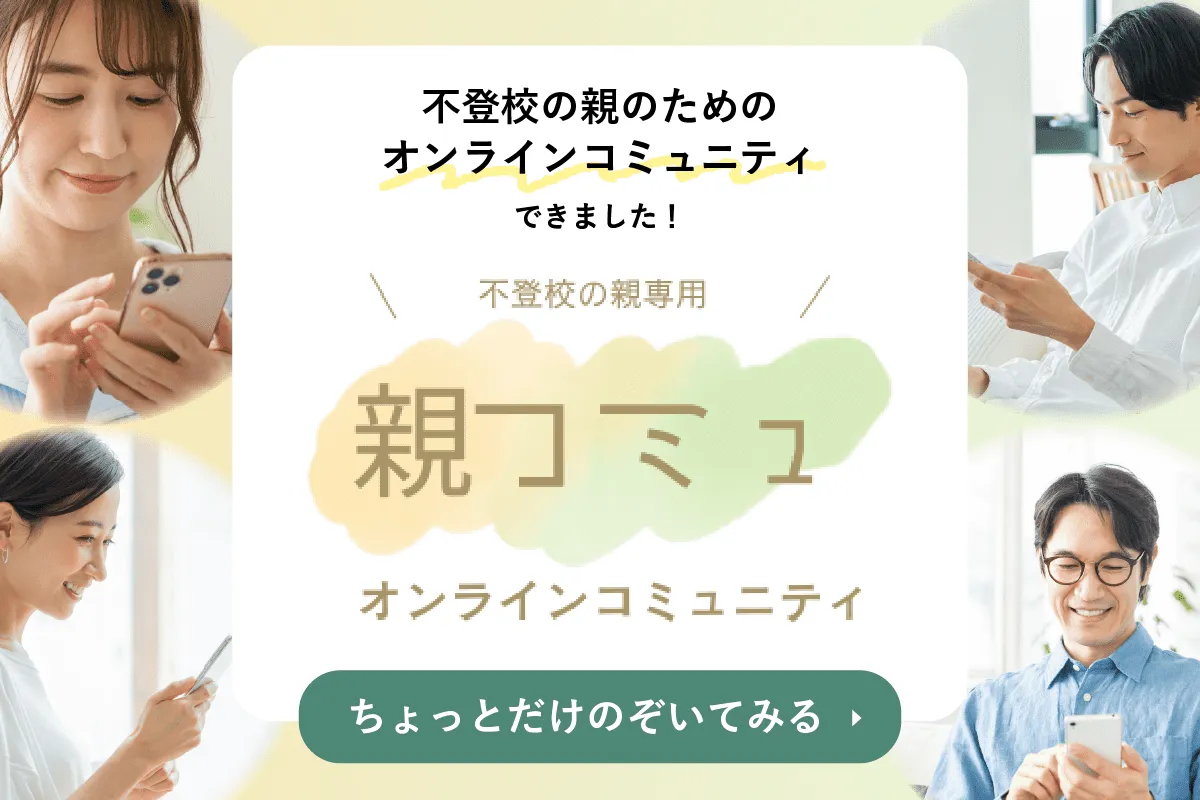発達障害による小学生の癇癪 親ができる7つの対応・相談先を紹介

![]()
![]()
小学生の癇癪に悩む親御さんの相談は、キズキにもたくさん寄せられます。
癇癪(かんしゃく)の例
- 急にスイッチが入ったように泣きわめく
- 汚い言葉をぶつける
- 家に帰らないと言って聞かない
- 友達に暴力を振ってしまう
このような小学生のお子さんの癇癪に疲れ、「育て方が悪かったのかな…」「しつけができていないのかも?」とご自身を責める親御さんは少なくありません。
ですが、小学生のお子さんが感情をコントロールできず癇癪を起すのは仕方のないことです。
そして、お子さんの癇癪は親御さんのせいではありません(大人でさえ、自身の感情コントロールに悩む人はたくさんいます)。
ただし、癇癪の原因に発達障害(グレーゾーン含む)が関係していることがあります。
この記事では、発達障害と小学生の癇癪の関係、癇癪への7つの対応、相談先、親御さんの息抜き方法などをお伝えします。
このコラムが、お子さんの癇癪が軽減されるきっかけとなりましたら幸いです。
私たち、キズキは、発達障害や不登校のお子さんを、13年間で3,000名以上サポートしてまいりました。無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。少しでも気になるようでしたら、お気軽にご連絡ください。
目次
幼児期から小学生までの癇癪

癇癪(かんしゃく)は、次のような意味です。
ちょっとしたことにも感情を抑えきれないで激しく怒り出すこと。また、そういう性質や、その怒り。
これを踏まえて、まずは幼少期と小学生の癇癪について、詳しく解説します。
①幼児期の癇癪
まずは、自己意識が芽生え始める2〜3歳頃の癇癪です。
「魔の2歳児」と言われるように、2歳頃から始まるのが「イヤイヤ期」です。イヤイヤ期は、一次反抗期とも呼ばれます。
この時期の子供は、何でも「自分がでやる!」と思うようになる一方で、失敗することも少なくありません。
そして、「うまくいかないこと」に対して癇癪を起こすのです。(参考:『きほんの発達心理学』佐伯素子他、おうふう)
また、その時に親が手助けをしたり「しつけ」として叱ったりすると、子供はさらに反発し癇癪がエスカレートすることがあります。
ただし、幼児期の癇癪は発達過程において必要なもので、5歳頃までに落ち着くことが多いです。
②小学生の癇癪
小学生になった6歳、7歳になっても、癇癪がおさまらない場合もあります。
しかし、成長の過程や速度は個人によって違っています。
つまり、「幼少期の癇癪は、必ず2歳から始まり5歳で終わる」「小学生になった7歳で癇癪を起すのはおかしい」わけはないのです。
もう少し月齢・年齢が上がることで、癇癪が怒らなくなることもあります。
また、癇癪の原因が「お子さん本人」ではなく、親御さんの子育てと関係することもあります(一生懸命子育てをしても、思うように育たないことは誰にでもあります)。
このケースは、今回の主旨から離れるので省略します。
ご自身の子育てに不安がある場合は、家族や学校の先生、市区町村の子育て担当課などに相談してみてもよいかもしれません。
そして、一部の子供の癇癪には、発達障害が関係することがあります(次章で詳しく解説します)。
癇癪など発達障害の特性による困りごとを抱えているあなたのための塾&家庭教師【キズキ】相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)
詳しく見る小学生の癇癪と発達障害の関係性

次に、小学生の癇癪と発達障害の関係を解説します。
この章では、『イラスト図解 発達障害の子どもの心と行動がわかる本』(田中康雄 西東社)に基づいてお伝えします。
発達障害とは
発達障害とは、生まれつき脳機能のバランスに偏りがある状態です。
脳には、集中力や文字を読む力や空気を読む力などのさまざまな機能があり、どんな人でもその働きにある程度のバラツキはあります。
そのなかで発達障害は、特に偏りの程度が激しく学校生活や友人関係に困難を抱える特性があることを指します。
また、発達障害は、主に次の3グループに分類されます。
- 1:自閉スペクトラム症(ASD)
コミュニケーション能力に困難があり、人間関係を築くことが苦手。こだわりが強く、感覚過敏であることも。 - 2:注意欠如・多動症(ADHD)
不注意・多動性・衝動性などによる行動があらわれやすい。 - 3:学習障害(LD)
知的障害ではないが、読む、書く、計算するなどの特定の分野が極端に苦手。
ただし、こうした特性は発達障害でなくても小学生なら誰にでもある程度は当てはまります。
また、「発達障害かどうか」は専門医でないと判断・診断できません。
そのため、まだ診断を受けていない場合は、一度専門医への相談も検討してみてください。
また、こうした特性(に伴う困難)があるにもかかわらず、発達障害の診断が出ない状態を、「発達障害のグレーゾーン」と言います。
発達障害のグレーゾーンについては、コラム「発達障害グレーゾーンの中学生を持つ親御さんができること5選」で詳しく解説しています。
発達障害による癇癪の原因
先述した通り幼児期の癇癪の原因は、「自分の思い通りにならないこと」にあります。
しかし、発達障害(グレーゾーン)による癇癪の原因は、「どうしていいかわからない強い不安や恐怖、葛藤、混乱」だと言われています。
ASDの小学生は、予期しない出来事に不安を覚えたり感覚過敏のために音や匂いを不快に感じたりすることで、突然怒り出すことがあります。
ADHDのうち衝動性の強い小学生は、喜怒哀楽のコントロールに困難があり、何らかの原因によりカッとなって癇癪を起こす傾向があるとも言われています。
このように、発達障害の特性がある子供は、周囲の人と「感じ方」が違うのです。
そのため、周囲の人が何でもないことでも、その子にとっては混乱の原因となり、癇癪に繋がることがあるのです。
発達障害による癇癪の例

発達障害の小学生が起こす癇癪には、次のようなものがあります。
発達障害の小学生が学校で起こす癇癪の具体例
- ドッジボールで負けてカッとなって友達を叩く
- 順番を待てずに前の子を押す
- 読書中にクラスメイトに話しかけられて怒る(周囲が本人の行動を妨げたことでパニックになる)
- クラスメイトから言われた冗談を、冗談と理解できずに怒る
発達障害の小学生が家庭で起こす癇癪の具体例
- 原因も見当たらないのに泣きわめく(理由のない不安)
- 親子でクッキーを作ったが思った通りにならず(本人の独特なこだわり通りのクッキーじゃなかったので)怒り出す
- 新調したセーターの肌触りが嫌で泣き出す(感覚過敏)
また、このような発達障害による癇癪が、友達関係に影響することを心配している親御さんもいるかもしれません。
コラム「発達障害の子どもの友達作りのために、親ができる11の方法」では、発達障害の子供の友達作りについて詳しく解説しています。気になる方はぜひご覧ください。
発達障害による癇癪は「わがまま」ではない
発達障害による癇癪は、発達障害の特性に由来する不安や混乱によるものであり、わがままではありません。
そのため、癇癪を起しても叱らず「癇癪を起こすほど子供が追い込まれている」と考えることが大切です。
また、お子さんの癇癪について親御さんだけで悩まずに、小児科やスクールカウンセラー、サポート団体などに相談してください。
相談先には、後ほど詳しくご紹介します。
発達障害の小学生の癇癪への対応
この章では、癇癪を起こす発達障害の特性がある小学生への対応方法をお伝えします。(こちらも、参考:田中康雄 西東社『イラスト図解 発達障害の子どもの心と行動がわかる本』)
ただし、有効な対応方法はお子さんごとに違います。
一番大切なことは、親御さん・ご家族だけで対応しないことです。
学校の先生や医療機関、発達障害の支援機関など、「専門的な知識・経験を持つ人」の力を借りましょう。
そうすることで、あなたのお子さんに適した具体的な対応が見つかりやすくなります。
また、これからお伝えする対応は、場所や場面によっては使えない場合もあります。
そのため、一つだけではなく、さまざまな対応を身につけることが大切です。
対応①癇癪の原因を把握する

お子さんの癇癪の原因を把握し、できる限り「原因となること・状況」が起きないようにすることが大切です。
癇癪の原因は、発達障害の特性とお子さんの性格によって「急な予定変更が苦手」「強いにおいが苦手」「急に友達に話しかけられるのが苦手」など、さまざまです。
パニック・癇癪の原因への対応例
- 集中している時に声をかけない(本人が納得するまで宿題をさせてから、次の行動に移すように声をかけるなど)
- 学校の時間割や持ち物は、前日に親子で確認する
- 首の詰まった服が苦手であれば、襟ぐりの大きな肌触りのいい服を用意する
- 友達に突然声を掛けられるのが苦手であれば、そのことを担任の先生に伝えておく
対応②子供の気持ちに寄り添う
お子さんの気持ちを理解しようとする姿勢をお子さんに見せることも大切です。
お子さんは、自分の気持ちをうまく伝えられないために、癇癪で感情を表現していることが考えられます。
小学生は、大人と比べて気持ちを表す適切な言葉や行動を知りません。
そして、発達障害の特性によって感情のコントロールが難しい場合もあります。
お子さんが癇癪に対して親御さんは怒りたくなることもがあるかもしれません。また、落ち着かせようとして疲れることもあると思います。
ですが、親御さん自身が落ち着いて「どうしてさっきは怒ったの?」と声をかけることが大切なのです。
こうした親御さんの姿勢を見たお子さんは、「自分と向き合ってくれている」と安心感を得られます。
また、お子さんの回答から「今後の具体的な対応」を考えるためヒントを得られるかもしれません。
ただし、繰り返すように「発達障害の小学生が、気持ちをうまく表現できないこと」はよくあるため、無理に理由を聞き出そうとしないことも大切です。
また、発達障害の特性があるお子さんは、独特な感性を持っており、周囲の人には理解できないことあります。
そのため、親御さんが発達障害のお子さんの気持ちや行動が理解できなくても、「親の努力不足」とご自身を責める必要はありません。
対応③癇癪が起きたら落ち着ける場所に移動する

子供が落ち着ける場所をあらかじめ決めておき、癇癪・パニックを起こしたらその場所に移動しましょう。
「場所」と「落ち着き」がお子さんの中でセットにすると、パニックや癇癪がおさまりやすくなります。
子供が落ち着ける場所の例
- 子供部屋
- ペットのいる場所
- 押し入れの中
学校でこの方法を実践するのは難しいかもしれませんが、一度担任の先生やスクールカウンセラーに相談してみてもよいかもしれません。
コラム「発達障害によるパニックの対応方法|サポート機関や進路についても解説」では、発達障害によるパニックの対応方法を解説していますので、こちらも参考になるかと思います。
対応④自傷行為はクールダウンまで見守る
癇癪を起こした際に、自分の手を噛んだり、頭を壁に打ちつけたりする自傷行為をするお子さんもいます。
無理に止めようとすると、意図せず周囲に危害を加えてしまうこともあるので、クールダウンするまでは見守ることが大切です。
※ただし、自傷行為は本人にさえ思わぬ大怪我につながる可能性もありますので、注意して見守りましょう。
また、今自傷傾向があるかどうかに関わらず、「自傷行為をしたら、具体的にどのように見守るのか」を、次章で紹介する相談先で確認・相談しておくことをオススメします。
対応⑤気持ちを表現する練習をする

これは、癇癪を起こさないようにするための対応です。
気持ちをあらわす表などを使用して、自分の気持ちが表のどの感情に当てはまるかを周りに伝える練習に取り組んでみてください。
感情を伝える練習をすることで、感情を癇癪として爆発させずに周囲に自分の気持ちを伝えられるようになるはずです。
【表の例「今の気持ちはどれかな?」】
- 1:イライラ
- 2:こまった
- 3:つかれた
- 4:ふつう
- 5:たのしい
お子さん本人が感情を伝えられると、周囲も「今、何がこの子の特性に合わないのか」を理解しやすくなるはずです。
対応⑥癇癪を起こさなかったときに褒める
これは、癇癪を起こさなかったときの対応です。
次のような場面で、お子さんを褒めるように心がけてみてください。
子供を褒めるタイミング例
- いつもなら癇癪を起こすような場面で、癇癪を起こさなかったとき
- 癇癪が終わって、気持ちが落ち着いてきたとき
不安や恐怖にから癇癪を起すお子さんを、頭ごなしに叱っても逆効果です。
逆に、癇癪を起さなかったときにお子さんを褒めると、「癇癪を起こさないことはいいことなんだ」「落ち着いた方がいいんだ」と、学びになります。
そして、不安や恐怖にかられてむやみに癇癪を起こす頻度は少なくなるはずです。
ただし、「癇癪を起こさずに、気持ちを自分の中にため込む」ことは、ストレスにつながる可能性があります。
先ほど紹介した方法などを練習して、癇癪以外の気持ちの表現方法を身につけることが大切です。
対応⑦薬物療法などの治療を受ける

発達障害の特性を抑えるために、医師の治療を受けることも一つの方法です。
治療の中には、発達障害の特性を抑えるための薬を飲む「薬物療法」もあります。
薬で衝動性などの特性が抑えることで、それに伴う癇癪が減ることがあるのです。
また、お子さん自身の精神的負担が減り、学校や人間関係でのトラブルの軽減にもつながることが期待できます。
とはいえ、薬物療法への不安が大きい親御さんもいらっしゃるかもしれません。
ですが、発達障害の薬は医師の判断によって処方されるものです。
実際に飲むかどうかは別として医師に相談することもできますので、気になる方は一度病院を受診することをオススメします。
なお、「医師」ではない人が処方する「薬」はオススメできません。
発達障害の小学生の癇癪を相談できる支援機関9選
発達障害よる小学生の癇癪は、「発達障害のサポート団体・機関」で相談できます。
専門家に相談することで、親子で「癇癪が起きた後の対応」や「癇癪を起こなさいための練習」、「癇癪以外の発達障害に関する対応」などを、より深く理解できるのです。
なお、公的な機関・団体は、お住まいの市区町村役所の子育て担当部署や障害福祉担当部署、総合窓口などで確認できます。
相談先①スクールカウンセラー・養護教諭

学校に在籍するスクールカウンセラーや養護教諭(保健室の先生)は、一番身近な相談先です。
また、相談以外にも、学校での癇癪に関して担任の先生などと連携しやすくなったり、地域の支援機関を紹介してもらえたりします。
公認心理師など心理の専門家や、元教員などの教育の専門家が、スクールカウンセラーとして週に何回か学校に来て心の相談を受け付けています。
子供本人だけでなく、保護者も相談できます。
(スクールカウンセラーのいない学校もあります。その場合は都道府県の教育委員会にカウンセラーがいることが多いので、まずは担任の先生に相談してみてください)
相談先②医療機関
医療機関とは、小児精神科や児童に詳しいクリニック、かかりつけの小児科などです。
かかりつけの病院があれば、これまでの成長の様子や特性を詳しく把握しているため、はじめに相談するとよいでしょう。
また、かかりつけ医から専門医へ紹介状を書いてもらえることもあります。
カウンセリングはさまざまな人が行っていますが、一般的には「臨床心理士・公認心理師」等の資格を持ったカウンセラーがオススメです(そのようなカウンセラーが在籍している病院もあります)。
癇癪の原因を突き止めるために、病院で受診したい気持ちはあるけど診断を受けることに不安がある方は、コラム「発達障害はどこに相談する?7つの相談先・窓口、発達障害の診断の流れも解説」も参考にしてみてください。
相談先③市区町村の子育て担当課・福祉担当課

お住まいの市区町村役所の、子育て担当課・福祉担当課でも相談できます。
具体的には、発達障害の相談を受け付けていたり、地域の医療機関・相談機関を紹介してもらえたりできるはずです。
相談先④発達障害支援センター
発達障害支援センターとは、各都道府県等に設置されている、発達障害の大人と子供を支援する公的な専門機関です。
幼児から成人までの発達障害の人の相談を受け付けています。
活動内容は各センターによって違っており、心理師によるカウンセリングを行っているところや医師による診察を行っているところもあります。
具体的な活動内容は、お住まいの地域のセンターに問い合わせることで確認できます。
相談先⑤保健所・保健センター
保健所・保健センターでは、保健師に相談できます。
保健師とは、厚生労働大臣免許を受けた、地域住民の健康相談を行う専門家です。
相談先⑥児童相談所
児童相談所は、各都道府県に設けられた「18歳未満の子供」を対象とした児童福祉のための専門機関です。
養護相談、保健相談だけでなく、発達障害など心の相談や子育てに関する相談も受け付けいています。
なお、児童相談所の補助機関として、児童家庭支援センターもあります。
相談先⑦教育センター・特別支援教育センター

教育センター・特別支援教育センターとは、各都道府県や政令指定都市等に設置されている教育機関です。教育に関する研究や、教員・子供・保護者を対象に、教育相談を受け付けています。
教育の現場に長く携わった人に、学習、いじめ、発達障害などの心理的な問題などの相談をすることも可能です。
また、必要に応じて心理師が相談に同席することもあります。
相談先⑧発達障害の「親の会」
親の会は、発達障害の子供を親が集まって、お互いの悩み相談や情報共有、専門家を招いての講習などを行っている団体の総称です。
親の会は全国にたくさんあり、その目的や活動内容は団体ごとに違っているので、悩みに合いそうな団体があれば、積極的に参加してみてください。
相談先⑨発達障害に理解のある家庭教師・学習塾

発達障害に理解のある家庭教師や学習塾もたくさんあります。(私たち、キズキもその一つです)
そうした家庭教師や学習塾では、発達障害の特性に合わせた勉強方法で学べることはもちろん、発達障害による癇癪を含むコミュニケーションや生活へのアドバイスを得られることが一般的です。
発達障害の子供の勉強に関連するコラム
発達障害の小学生の癇癪に疲れた時の息抜き方法
癇癪を起こす小学生のお子さんの子育ては、本当に大変です。
親御さんが疲れたと感じるのは、当然のことと言えます。
しかし、親御さんが疲れた状態でイライラしていると、お子さんは大きな不安を覚えさらなる癇癪に繋がる可能性があります。
そのため、お子さんはもちろん親御さん自身のためにも、疲れたと感じた際は積極的に休養をとることが大切なのです。
キズキでオススメしている親御さんの息抜き方法をご紹介します(より具体的な実施法や内容は、私たちにお気軽にご相談ください)。
息抜き法①家事代行を利用する

疲れたときは家事代行サービスなどを利用して、日常の負担を減らすことが大切です。
また、自分や配偶者が家事を行う場合は、完璧を求めず「必要最低限でいい」と考えましょう。
息抜き法②楽しみを見つける
趣味やリフレッシュの時間を意識的に作り、疲れた気持ちを癒すことも大切です。
息抜き法③放課後等デイサービスを利用する

6歳~18歳までの発達障害の子供が、放課後や夏休みなどに過ごせる「放課後等デイサービス」がお近くにあるか、調べてみましょう。
また、市町村が発達障害のお子さんを預かるサービスを行っている場合もあります。
息抜き法④親の会・ペアレントトレーニングに参加する
同じ悩みを持つ親や、小学生の時期を終えた「子育ての先輩」の話を聞くことで、悩みや不安が解消されることがあります。
また、子供の癇癪に関する悩みや疲れを第三者に聞いてもらうことで、気持ちがスッキリするかもしれません。
息抜き法⑤カウンセリングを受ける

親自身や家庭内に不安・悩みがある場合は、心療内科などでカウンセリングを受けることを検討してみてください。
前章で紹介した相談先では、お子さんのことだけでなく親御さん自身の「子供の癇癪で疲れた」「自分だけでは手がつけられない」などの悩みなども相談できることが多いです。
まとめ~発達障害の小学生の癇癪は専門家に相談を~

小学生の癇癪には、発達障害の特性が関係していることがあります。
しかし、癇癪の原因が発達障害であっても、お子さんの特性を知り適切な対応をすれば、十分に改善できます。
また、お子さんの癇癪が手がつけられない状況であっても、親御さんやご家庭だけで悩む必要はありません。
発達障害が関係するかどうかに関わらず、子どもの癇癪について相談できる支援機関はたくさんあるのです。
この記事が、お子さんと、親であるあなたのお役に立ったなら幸いです。
さて、私たちキズキは、発達障害や不登校やなどのお子さんのための塾&家庭教師です。
13年間で3,000名以上のお子さん・親御さんをサポートしてまいりました。
発達障害・不登校・癇癪などの無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。
少しでも気になる方は、お気軽にご連絡ください。

監修:安田祐輔
やすだ・ゆうすけ。発達障害(ASD/ADHD)によるいじめ、転校、一家離散などを経て、不登校・偏差値30から学び直して20歳で国際基督教大学(ICU)入学。卒業後は新卒で総合商社へ入社するも、発達障害の特性も関連して、うつ病になり退職。その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。経歴や年齢を問わず、「もう一度勉強したい人」のために、完全個別指導を行う。また、不登校の子どものための家庭教師「キズキ家学」、発達障害やうつ病の方々のための「キズキビジネスカレッジ」も運営。
【新著紹介】
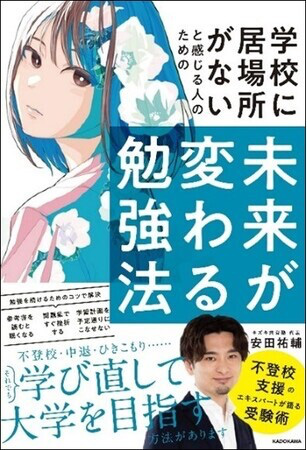
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法』
(2022年9月、KADOKAWA)
Amazon
KADOKAWA公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)
【著書など(一部)】
『暗闇でも走る(講談社)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』)
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

共同監修:半村進
はんむら・すすむ。1982年、茨城県生まれ。東京大学文学部卒。
小学校時代から転校を繰り返し、運動ができないこと、アトピー性皮膚炎、独特の体形などから、いじめの対象になったり、学校に行きづらくなっていたことも。大学に入学してようやく安心できるかと思ったが、病気やメンタルの不調もあり、5年半ほど引きこもり生活を送る。30歳で「初めてのアルバイト」としてキズキ共育塾の講師となり、英語・世界史・国語などを担当。現在はキズキの社員として、不登校・引きこもり・中退・発達障害・社会人などの学び直し・進路・生活改善などについて、総計1,000名以上からの相談を実施。